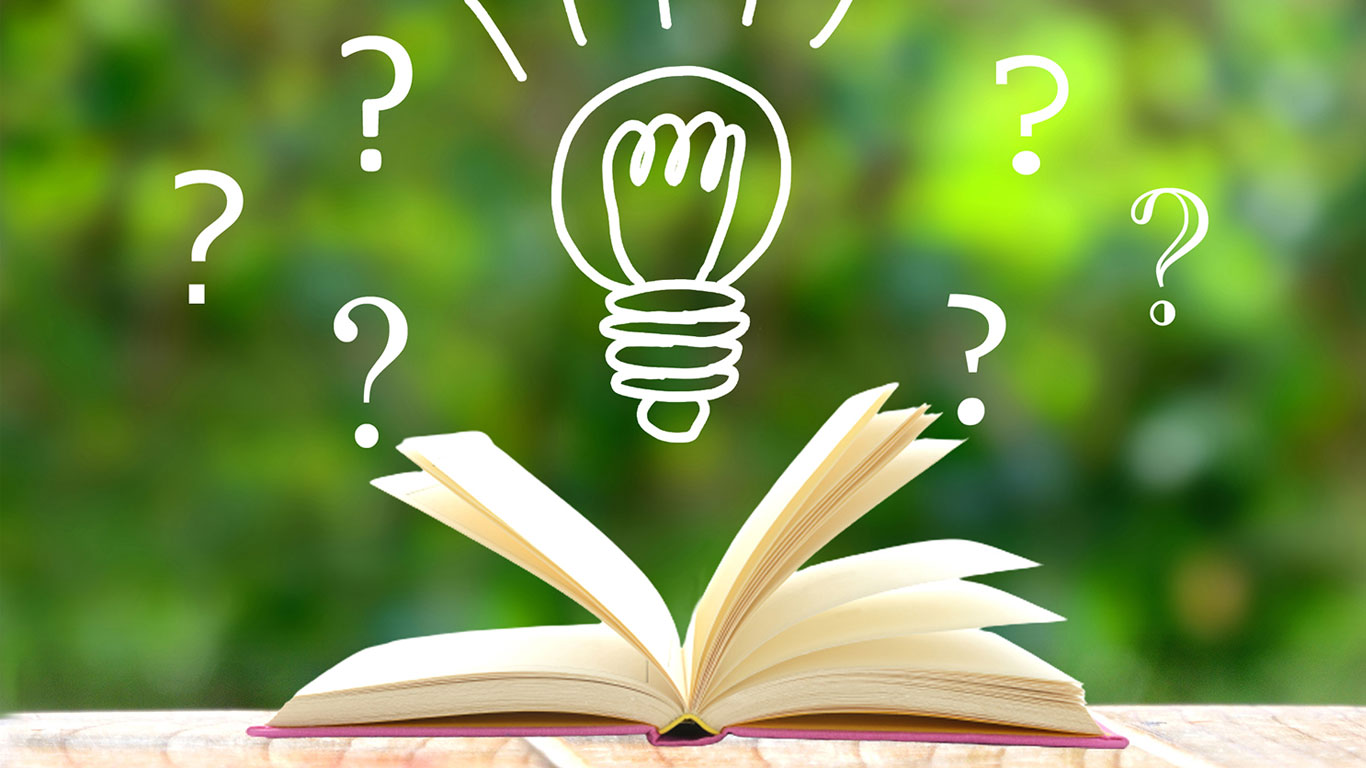結露は大敵、健康面でもマイナス
外気が厳しい季節となっておりますね。
寒さに負けず、現在、お客様の建築の為の申請関係に備える営業の福井です。
外気温が大幅に下がる冬は一年中でもっとも結露が発生しやすい時期です。
結露を放っておくと人間の健康にも害があるし、建物自体を傷める原因となります。
結露は住まいにどんな悪影響があるのか。結露を最小限に抑えるにはどうすればいいのか。
急に温度が下がると空気中の水蒸気が水になる。 結露の要因
空気が冷たいものに触れて急に温度が下がると、それまで空気に含まれていた水蒸気が水となってその表面にあらわれる。これが結露です。なぜ空気の温度が下がると結露が発生するのか。
「空気は温度が高いほど多くの水蒸気を含むことができます。空気を器に例えると、そこにためられる水の量は器が大きい(温度が高い)ほど多く、器が小さい(温度が低い)ほど少ない。ですから温度が下がって器が小さくなると、今まで入っていた水が溢れてしまうことがある。結露ができるのも、これと同じ仕組みです」
冬に結露が多いのは外気温の低さや換気が足りないことが原因です。
外が寒く外壁や窓ガラスが冷たくなっている一方で、室内は暖かく空気中の水蒸気量が多いことです。例えば冬は室内で水蒸気を発生するタイプの暖房器具を使う機会が多かったり、外気が乾燥するため加湿器を使う機会も多い。その結果、冬は室内の湿度が意外に高くなりやすいのだ。さらに冬は窓を閉め切っている時間が長く、換気の回数が少ないため室内に湿気がたまりやすい。これも結露しやすい原因となります。
放置するとカビが生え、ぜん息など健康面でもリスクが高まる
人間の健康への影響はどうかとなると、結露でぬれた壁や床などを放置しておくと、カビが生える。カビはさまざまな病気の原因になり健康面で住んでいる人に害をおよぼします。
例えばぜん息の主要な原因物質のひとつがこのカビだと言われています。そしてぜん息のもうひとつの主要な原因物質であるダニがこのカビをエサとしている。そのため、カビが増えればそれをエサとするダニも増えるという悪循環がおこる。つまり小さな子どもやお年寄りのいる家庭では、結露がぜん息のリスクをどんどん高くしていくわけだ。
また最近ではカビの一種・トリコスポロンが引き起こす『夏型過敏性肺炎』や、カビをエサとして大量発生したコナヒョウヒダニが原因で起こる『パンケーキ症候群』など、あたらしい病気も報告されており、結露対策は健康面からもますます重要になってきています。
月別アーカイブ
- 2025年 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
- 2024年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
- 2023年 12月 11月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
- 2022年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
- 2021年 12月 11月 10月 9月 7月 6月 5月 4月 3月
- 2020年 11月 10月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
- 2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
- 2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
- 2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
- 2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
- 2015年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
- 2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
- 2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
- 2012年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
- 2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月